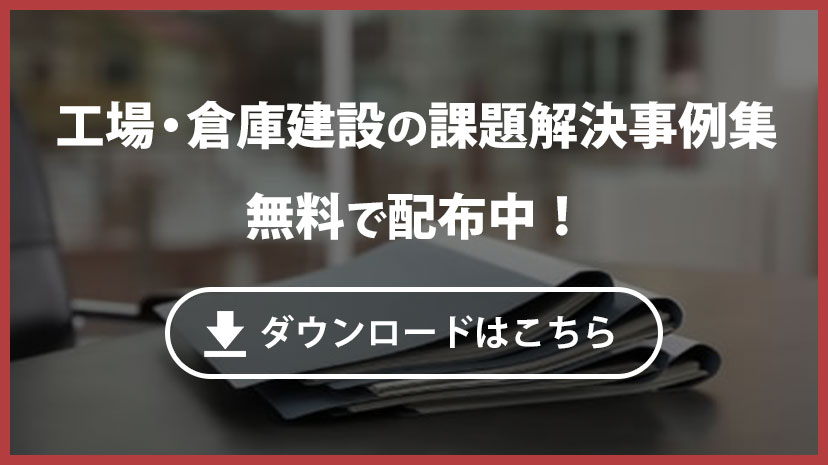冷蔵冷凍倉庫の断熱・冷却機械は「一括発注」か「分離発注」か?メリット・デメリットを徹底解説
投稿日:2025.10.23
更新日:2025.11.26
お役立ち情報

冷蔵冷凍倉庫は、保管に適した温度帯を維持するための冷却機械も大切ですが、そのエネルギーを逃がさないようにするための工事として断熱工事が非常に重要になります。
冷蔵冷凍倉庫の新設や改修工事を行う際は、適切な温度帯を維持するための冷却機械の選定と、外部からの熱の侵入を防ぎ、冷却装置の効率を高めるための断熱工事が行われるのですが、それぞれの工事の発注先はどうすれば良いのでしょうか?一般的には、断熱と冷却機械の設置工事については、分離発注されることが多いです。しかし、両工事を分離発注にした場合、窓口が増え、工事期間中のやりとりなどが複雑化するうえ、稼働後に何らかの問題が発覚した際には、責任の所在があいまいになるといった問題が発生します。
一方、断熱・冷却機械に係わる工事を一括で依頼すると、工事の日程調整などが容易になるなど、さまざまなメリットが得られます。そこで本記事では、冷蔵冷凍倉庫における断熱・冷却機械の工事について、分離発注、一括発注それぞれのメリット・デメリットについてまとめます。
Contents
断熱・冷却機械の工事を分離発注する場合のメリット・デメリット
プロジェクトの規模や内容、要求される専門性などによっても分離発注と一括発注のどちらが好ましいかは変わります。まずは、分離発注を選択する場合のメリットとデメリットを紹介します。
分離発注のメリットについて
断熱工事と冷却機械を分離発注する場合には、以下のようなメリットがあるとされています。
-
コストの削減効果
分離発注の場合、各工事を専門業者に直接発注することができるようになるため、プロジェクト全体で見ると、コストダウンにつながる可能性があります。これは、各工事業者を自社で選定、直接契約を行うこと形となるため、元請け業者の中間マージンが削減できる可能性があるためです。 -
専門性が確保できる
分離発注の場合、断熱工事は断熱の専門業者に依頼する、冷却装置の選定についても専門家に相談する形となります。つまり、それぞれの工事を専門業者に確実に発注する形となるため、より高度で専門的な対応が期待できるようになります。 -
品質の向上
断熱、冷却機械について、それぞれの専門業者に発注する形となり、担当範囲に責任を持たせることができ、手抜き工事や施工不良などの問題が発生するリスクを低減することができます。分離発注の場合、それぞれの専門家が担当範囲の工事を管理する形となるため、より厳格な品質管理が実施され、施工品質の向上が期待できます。 -
柔軟な対応が受けられる可能性が高い
分離範疇の場合、各工事について、それぞれの専門業者と直接やり取りができるようになるため、資材や仕様に関して、個別のニーズに合わせて自由に選択できるようになります。一括発注の場合、業者が扱う製品や技術に制約されることがあるのですが、分離発注の場合は「より省エネな冷却システムを採用したい」「特定の性能を追求したい」など、個別のニーズに合わせて業者を選定するなど、自由度が高くなる場合が多いです。また、工事や納品のタイミングは個別に調整することができるので、工程も柔軟に管理できるようになります。
分離発注には、上記のようなメリットがあります。
分離発注のデメリットについて
一方、分離発注は手間や管理コストが増えるなど、いくつかのデメリットも存在するので、以下の点については注意が必要です。
-
管理負担の増大リスク
分離発注の場合、作業範囲ごとに専門業者とやりとりする必要が出てきます。工事を進行していく上では、スケジュールの管理や品質管理、コスト管理などを行わなければならないのですが、窓口が増えればその分手間や負担も増大していきます。 -
業者間の調整が必要になる
分離発注の場合、断熱工事と冷却機械の施工タイミングや、責任範囲の調整など、業者間の連携を行わなければいけません。一括発注の場合、元請け業者が上手く調整してくれるものの、分離発注の場合は、自社の担当者が間に入って調整しなければいけません。この場合、連絡や調整が不十分になる可能性があり、最悪の場合、工事の遅延などといったトラブルを誘引する可能性があります。 -
責任の所在があいまいになる
分離発注の場合、稼働後に何らかの不具合が発生した際、その原因が断熱と冷却機械のどちらにあるのか明確化させることが難しいです。そのため、責任の所在があいまいになることで、その後の対処が遅れるなど、さらなる問題を誘引する可能性があります。 -
全体像の把握が難しい
分離発注の場合、各工事は個別のスケジュールで進みます。そのため、プロジェクト全体として見た時には、全体としての進捗状況やコストの全体像が把握しにくくなるという問題が生じます。
分離発注には、上記のような点がデメリットとされています。
断熱・冷却機械の工事を一括発注する場合のメリット・デメリット
それでは次は、一括発注する場合のメリットとデメリットについて解説します。
冷蔵冷凍倉庫の断熱・冷却機械の工事については、分離発注されることが多いと紹介しました。しかし、一括発注の場合は、設計から施工、メンテナンスまでをスムーズに進めることができるなどのメリットがあります。特に、冷蔵冷凍倉庫の建設・改修実績が豊富な業者に依頼することができれば、下で紹介するデメリットも解消できるでしょう。
ここでは、断熱と冷却機械を一括発注する場合のメリットとデメリットをまとめてみます。
一括発注のメリットについて
一括発注のメリットは以下のような点です。
-
管理負担の軽減
一括発注の場合、窓口が一本化されることになります。そのため、プロジェクト全体の管理を一元的に行うことができるようになるため、業者との連絡や調整にかかる手間を大幅に削減することができるなど、発注者側の管理負担が大幅に軽減されます。稼働後にトラブルなどが発生した場合も、責任の所在が明確なので、迅速な対応が期待できるなど、将来的な管理負担も軽減することが期待できます。 -
責任の所在が明確化される
分離発注の場合、不具合などのトラブルが発生した際、その責任がどこにあるのかがあいまいになるという点がデメリットだと紹介しました。一方、一括発注の場合、トラブル時の責任なども元請け業者が一括で請け負うことになるので、責任の所在が明確化されます。 -
効率の向上と品質安定
各作業を受け持つ下請け業者については、元請け業者が統括するため、スケジュールの調整や工程ごとの連携などもスムーズに進みます。複数の業者との調整が不要となり、スケジュール管理が簡略化されると、全体の工期短縮も期待することができるでしょう。また、元請け業者一社がプロジェクト全体を一貫して管理することになれば、施工品質のばらつきも防ぐことができ、安定的な品質を期待することができます。
一括発注のデメリットについて
次はデメリットについてです。
-
コスト増の可能性がある
一括発注の場合、発注を請け負う元請け業者の中間マージンが発生する場合があり、分離発注に比べてコストが高くなる傾向があるとされています。 -
対応範囲が限定されるなど、専門性が限定される恐れがある
一括発注の場合、作業を担う下請け業者は元請け業者が選定します。そのため、発注者が希望する専門性の高い業者が選べない可能性があります。
一括発注に関しては、上記のような点がデメリットになると言われることが多いです。
ただ、一括発注の場合、設計から施工までを一貫して請け負ってくれる企業に発注することができれば、各業者との個別の契約手続きが不要となり、事務コストや中間マージンを削減することができるので、上で紹介したコストの問題が解消できる可能性があります。また、断熱と冷却を統合的に設計することができる技術力の高い企業に発注した場合、熱負荷を最小限に抑え、冷却機器の運転時間を短縮することが期待できます。この場合、稼働時のエネルギー消費量が少なく抑えられるため、電気代の削減が期待できます。さらに、冷却機械への負担が少なくなれば、それだけ機器の摩耗が少なくなり、長寿命化に繋がる可能性が考えられ、将来的なメンテナンスや修理にかかるコストも削減できるでしょう。
結論として断熱、冷却機械の工事については、スキルや技術力が高く、冷蔵冷凍倉庫の実績を豊富に持つ業者に一括発注するという方法がベストと考えられます。
まとめ
今回は、冷蔵冷凍倉庫の断熱工事と冷却機械の設置について、一括発注と分離発注それぞれのメリット・デメリットを解説しました。
記事内でもご紹介した通り、断熱工事と冷却機械については、それぞれを専門とする業者に分離発注されることが多いです。これは、分離発注の方がコスト面でのメリットが大きいと考えられているからなのですが、その一方で、発注者には高い管理能力が求められるという点に注意しなければいけません。
一括発注の場合、窓口が一本化されることで設計から施工、メンテナンスまでをスムーズに進めることができるため、適切な業者を選定することができれば、中長期的な視点で考えると、コスト面でも有利に働く可能性が高いです。工事の日程調整が容易で工期短縮が期待できる、稼働後の責任の所在が明確になるといったことを考えると、実績のある会社に一括発注する方式がベストです。
冷蔵冷凍倉庫の建設、断熱工事、冷却機械の設置をご検討の方は実績豊富なRisokoにぜひご相談ください。
関連記事
ARCHIVE
TAG
- #バーコードリーダー
- #IoT機器
- #冷凍
- #冷蔵
- #リノベーション
- #法改正
- #冷蔵冷凍倉庫
- #発注
- #断熱
- #冷却
- #改正物流効率化法
- #物流統括監理者
- #倉庫業法施行規則
- #温度区分
- #太陽光パネル
- #食品物流センター
- #動画開設
- #配棟計画
- #パレット共通化
- #レンタルパレット
- #大阪万博
- #建築費動向
- #トラックGメン
- #ブラック荷主
- #物流クライシス
- #建設準備
- #グラフ
- #建築費
- #ドライバー不足
- #立地
- #2024年問題
- #3PL
- #3温度帯
- #4温度帯
- #AGV
- #AI
- #AVG
- #CAS冷凍
- #EC
- #FSSC22000
- #GDPガイドライン
- #IoT
- #IT
- #LED
- #RiSOKOセミナー
- #Society 5.0
- #Third Party Logistics
- #エアコン
- #カーボンニュートラル
- #ガソリン
- #グッズ
- #コールドチェーン
- #コロナ
- #コロナ禍
- #システム建築
- #タグを削除: RiSOKOセミナー RiSOKOセミナー
- #デバンニング
- #トラック待機時間
- #バンニング
- #ひさし
- #ピッキング
- #フォークリフト
- #プラスチック削減
- #フルフィルメント
- #プロトン凍結
- #フロン排出抑制法
- #フロン管理義務
- #マテハン
- #マテハン機器
- #メディカル物流
- #ラック
- #リチウムイオン蓄電池
- #ロボット
- #ロボット化
- #中小企業支援策
- #事故事例
- #人手不足
- #人材不足
- #低温倉庫
- #低温物流
- #保安距離
- #保有空地
- #保管効率
- #保管場所
- #保管温度帯
- #倉庫
- #倉庫の強度
- #倉庫の種類
- #倉庫建設
- #倉庫建設コンサルタント
- #倉庫新築
- #倉庫業法
- #倉庫火災
- #免震
- #共同物流
- #冷凍倉庫
- #冷凍自動倉庫
- #冷凍食品
- #冷蔵倉庫
- #冷蔵庫
- #削減
- #労働時間
- #労働災害
- #医療機器
- #医療物流
- #医薬品
- #医薬品の物流業務
- #医薬品保管
- #医薬品倉庫
- #危険物
- #危険物倉庫
- #危険物施設
- #営業倉庫
- #国際規格
- #土地
- #地震
- #地震対策
- #基礎知識
- #安全
- #安全対策
- #定期点検
- #定義
- #対策
- #屋内タンク貯蔵所
- #屋内貯蔵所
- #工場
- #工場の衛生管理
- #建築基準法施行令
- #建設計画
- #従業員
- #感染予防
- #技術
- #換気設備
- #改修工事
- #政令
- #新型コロナウイルス
- #新築
- #施設設備基準
- #機能倉庫建設
- #水害
- #水害対策
- #治験薬
- #法律
- #消防法
- #消防設備
- #温度管理
- #火災
- #火災対策
- #災害
- #無人搬送ロボット
- #無人搬送車
- #無人配送車
- #燃料費
- #物流
- #物流DX
- #物流センター
- #物流倉庫
- #物流倉庫新設
- #物流倉庫自動化
- #物流拠点
- #物流業界
- #物流総合効率化法
- #物流課題
- #特殊倉庫
- #用途地域
- #異物混入
- #着工床面積
- #空調
- #結露
- #耐震工事
- #職場認証制度
- #自動倉庫
- #自動化
- #自動車運送事業者
- #衛生管理
- #補助金
- #規制緩和
- #調理器具
- #貸倉庫
- #軽油
- #適正流通ガイドライン
- #関西物流展
- #防災
- #防災用品
- #防爆構造
- #集中豪雨
- #電気代
- #電気代削減方法
- #静電気
- #静電気対策
- #非危険物
- #非接触
- #食品倉庫
- #食品物流
- #食品衛生法
もっと見る▼