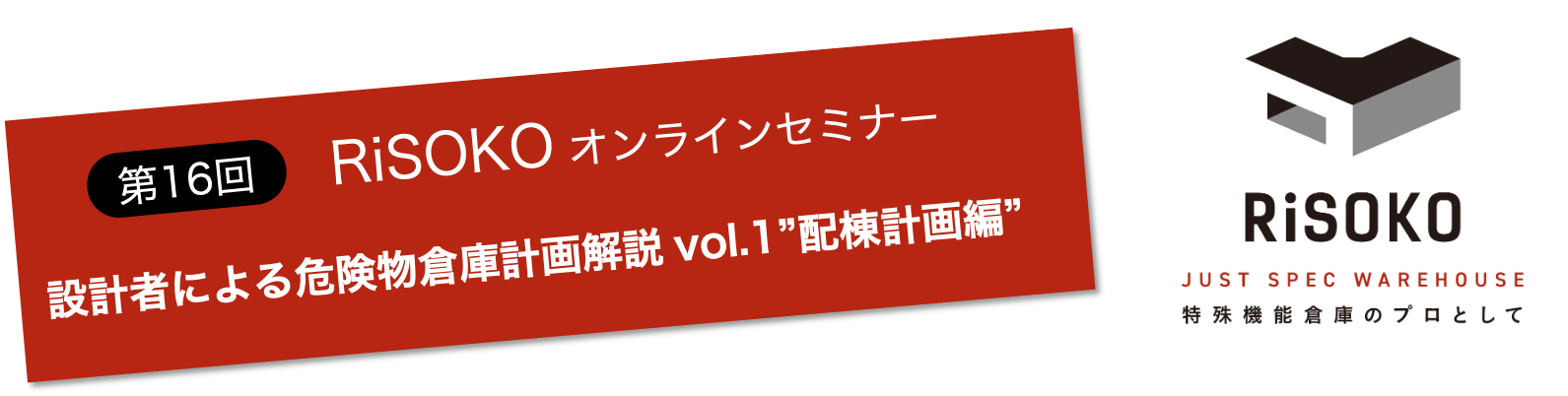簡単にわかる【危険物の基礎知識】危険物倉庫で働く方は要確認
投稿日:2020.01.06
更新日:2024.03.21
お役立ち情報

危険物倉庫で働く従業員である限り、「危険物とは何か?」という基礎知識を持っていなければいけません。一般の方であれば、『危険物』などと聞くと、違法ドラッグや毒物、劇物などをイメージする人が多いかもしれませんが、危険物倉庫における危険物とはあくまでも「消防法で定義された危険物」となるのです。
それでは、消防法で定義されている危険物にはどのようなものがあるのでしょうか?
消防法で定義されている危険物とは、「通常の状態で保管・放置しておくと、引火性・発火性があり、火災や爆発、中毒などの災害につながる危険がある物質」を指しており、もう少しわかりやすく紹介すると「火災を発生させる危険性の高い物質」を指しているのです。この危険物の中にはガソリンや灯油など、私たちの生活に非常に身近な物質も入っています。
危険物倉庫とは、これらの火災を発生させる危険がある物質について、一定以上の量を保管しておく場所となるのですが、そこで働く従業員は「危険物がどのように定義されて、どのような性質を持っているのか?」は学んでおきましょう。そこで今回は、消防法が定める危険物の基礎知識を簡単にご説明します。
Contents
そもそも『消防法』とは?
それではまず、危険物を定めている消防法について簡単にご紹介します。消防法とは、火災の予防・警戒・鎮圧による生命・身体・財産の保護・被害軽減を目的として定められている法律で、簡単に言うと火災から人々の生命を守るために作られた法律です。
この消防法の中には、危険物に関する条文があり、以下のように定義されているのです。
消防法第二条第7項
危険物とは、別表第一の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。
引用:e-Gov 消防法
上記のように、消防法によって危険物が定義されているのです。以下でもう少し詳しくみていきましょう。
危険物には『可燃物』と『支燃物』がある
危険物の基礎知識としてまずおさえておきたいのは、「危険物には可燃物と支燃物がある」ということです。もちろんどちらにしても、火災に重大な影響を与えることに変わりはないのですが、それぞれの性質はおさえておきましょう。
- 可燃物とは
可燃物は、燃えやすい性質を持っている物質のことです。例えば、ガソリンや灯油、軽油など私たちの身近にある引火性の高い物質や、ニトログリセリンやトリニトロトルエンなどの爆弾の材料になるような物質があります。 - 支燃物とは
支燃物は、少し複雑なのですが、物質自体は不燃性であるが、酸素供給源としての働きを持ち、上述した可燃物の燃焼を促進させる物質を指しています。硝酸などがこれにあたります。
消防法別表で定められている危険物とは?
それでは上述した消防法の中に出てくる『消防法別表』が何なのかもご紹介しておきましょう。
| 類別 | 性質 | 品名 |
|---|---|---|
| 第1類 | 酸化性固体 | 1 塩素酸塩類 |
| 2 過塩素酸塩類 | ||
| 3 無機過酸化物 | ||
| 4 亜塩素酸塩類 | ||
| 5 臭素酸塩類 | ||
| 6 硝酸塩類 | ||
| 7 よう素酸塩類 | ||
| 8 過マンガン酸塩類 | ||
| 9 重クロム酸塩類 | ||
| 10 その他のもので政令で定めるもの | ||
| 11 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの | ||
| 第2類 | 可燃性固体 | 1 硫化りん |
| 2 赤りん | ||
| 3 硫黄 | ||
| 4 鉄粉 | ||
| 5 金属粉 | ||
| 6 マグネシウム | ||
| 7 その他のもので政令で定めるもの | ||
| 8 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの | ||
| 9 引火性固体 | ||
| 第3類 | 自然発火性物質 および 禁水性物質 |
1 カリウム |
| 2 ナトリウム | ||
| 3 アルキルアルミニウム | ||
| 4 アルキルリチウム | ||
| 5 黄りん | ||
| 6 アルカリ金属およびアルカリ土類金属 | ||
| 7 有機金属化合物 | ||
| 8 金属の水素化物 | ||
| 9 金属のりん化物 | ||
| 10 カルシウムまたはアルミニウムの炭化物 | ||
| 11 その他のもので政令で定めるもの | ||
| 12 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの | ||
| 第4類 | 引火性液体 | 1 特殊引火物 |
| 2 第1石油類 | ||
| 3 アルコール類 | ||
| 4 第2石油類 | ||
| 5 第3石油類 | ||
| 6 第4石油類 | ||
| 7 動植物油類 | ||
| 第5類 | 自己反応性物質 | 1 有機過酸化物 |
| 2 硝酸エステル類 | ||
| 3 ニトロ化合物 | ||
| 4 ニトロソ化合物 | ||
| 5 アゾ化合物 | ||
| 6 ジアゾ化合物 | ||
| 7 ヒドラジンの誘導体 | ||
| 8 ヒドロキシルアミン | ||
| 9 ヒドロキシルアミン塩類 | ||
| 10 その他のもので政令で定めるもの | ||
| 11 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの | ||
| 第6類 | 酸化性液体 | 1 過塩素酸 |
| 2 過酸化水素 | ||
| 3 硝酸 | ||
| 4 その他のもので政令で定めるもの | ||
| 5 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの |
参考:wikibooks
少し長いですが、消防法別表とは上記の表のことを指しています。
さらに、消防法の条文中にある「同表に定める区分に応じ、同表の性質欄に掲げる性状を有するもの」については、上記の別表の品名欄に示されている物質で、性質の欄に書いてある『性質』を持っているものという意味となります。そうは言っても、「酸化性固体」や「引火性液体」がどのような性質を持つものなのかイマイチ分からない人も多いことでしょう。
以下でそれぞれの性質が持つ特徴もご紹介しておきますので、覚えておきましょう。
危険物の分類ごとの性質は?
危険物は、持っている特徴によって6つに分類されています。それぞれの性質は以下のようになっています。
- 第1類 酸化性固体
他の物質を強く酸化させる性質があり、可燃性と混合したときに、『熱・衝撃・摩擦』により、きわめて激しい燃焼を起こさせる固体。 - 第2類 可燃性固体
それ自体が燃えやすい、もしくは40度未満などの低温でも引火しやすい性質がある固体。 - 第3類 自然発火性物質および禁水性物質
空気、水に触れることで発火もしくは可燃性のガスを発生させる性質がある固体または液体。 - 第4類 引火性液体
引火しやすい液体。 - 第5類 自己反応性物質
加熱分解などによって爆発の恐れがある固体や液体。通常、物が燃焼するには酸素が必要ですが、このカテゴリーの物質は分子内に酸素を含んでおり、空気に触れなくても燃焼が進む。 - 第6類 酸化性液体
第1類と同様に、他の物質の燃焼を促進させる性質をもつ液体。刺激臭を有する物質が多い。
危険物の取扱に必要な資格
危険物を大量に製造・保管・取扱する場所では専門知識を持った管理責任者が必要になります。この役割を担うのが危険物取扱者です。
危険物取扱者は、甲・乙・丙の3種類があります。
この甲・乙・丙の資格によって取り扱いができる危険物の種類が異なります。
甲種は、実務経験、学校の専門課程での履修など受験資格がありますが、その他の乙・丙は誰でも受験することができます。
危険物倉庫建設のポイントはこちら
まとめ
今回は、危険物倉庫で働く従業員がおさえておきたい危険物の基礎知識をご紹介しました。本稿でご紹介したように、危険物とは「火災を発生させる危険性の高い物質」のことを指しており、消防法によって定義されています。ここで注意しておきたいのは、消防法で定められている危険物は、固体と液体のみで「気体の危険物はない」ということです。プロパンガスやアセチレンガスなどは、皆さんもご存知のように、可燃性のある気体で火災を引き起こす危険性があるのですが、消防法上では危険物に該当しないのです。
危険物について深く調べてみると、意外と知らないことも多いと思いますので、危険物倉庫で働くのであれば、ぜひ詳しく調べてみるのをオススメします。
関連記事
ARCHIVE
TAG
- #食品物流センター
- #動画開設
- #配棟計画
- #パレット共通化
- #レンタルパレット
- #大阪万博
- #建築費動向
- #トラックGメン
- #ブラック荷主
- #物流クライシス
- #建設準備
- #グラフ
- #建築費
- #ドライバー不足
- #立地
- #2024年問題
- #3PL
- #3温度帯
- #4温度帯
- #AGV
- #AI
- #AVG
- #CAS冷凍
- #EC
- #FSSC22000
- #GDPガイドライン
- #IoT
- #IT
- #LED
- #RiSOKOセミナー
- #Society 5.0
- #Third Party Logistics
- #エアコン
- #カーボンニュートラル
- #ガソリン
- #グッズ
- #コールドチェーン
- #コロナ
- #コロナ禍
- #システム建築
- #タグを削除: RiSOKOセミナー RiSOKOセミナー
- #デバンニング
- #トラック待機時間
- #バンニング
- #ひさし
- #ピッキング
- #フォークリフト
- #プラスチック削減
- #フルフィルメント
- #プロトン凍結
- #フロン排出抑制法
- #フロン管理義務
- #マテハン
- #マテハン機器
- #メディカル物流
- #ラック
- #リチウムイオン蓄電池
- #ロボット
- #ロボット化
- #中小企業支援策
- #事故事例
- #人手不足
- #人材不足
- #低温倉庫
- #低温物流
- #保安距離
- #保有空地
- #保管効率
- #保管場所
- #保管温度帯
- #倉庫
- #倉庫の強度
- #倉庫の種類
- #倉庫建設
- #倉庫建設コンサルタント
- #倉庫新築
- #倉庫業法
- #倉庫火災
- #免震
- #共同物流
- #冷凍倉庫
- #冷凍自動倉庫
- #冷凍食品
- #冷蔵倉庫
- #冷蔵庫
- #削減
- #労働時間
- #労働災害
- #医療機器
- #医療物流
- #医薬品
- #医薬品の物流業務
- #医薬品保管
- #医薬品倉庫
- #危険物
- #危険物倉庫
- #危険物施設
- #営業倉庫
- #国際規格
- #土地
- #地震
- #地震対策
- #基礎知識
- #安全
- #安全対策
- #定期点検
- #定義
- #対策
- #屋内タンク貯蔵所
- #屋内貯蔵所
- #工場
- #工場の衛生管理
- #建築基準法施行令
- #建設計画
- #従業員
- #感染予防
- #技術
- #換気設備
- #改修工事
- #政令
- #新型コロナウイルス
- #新築
- #施設設備基準
- #機能倉庫建設
- #水害
- #水害対策
- #治験薬
- #法律
- #消防法
- #消防設備
- #温度管理
- #火災
- #火災対策
- #災害
- #無人搬送ロボット
- #無人搬送車
- #無人配送車
- #燃料費
- #物流
- #物流DX
- #物流センター
- #物流倉庫
- #物流倉庫新設
- #物流倉庫自動化
- #物流拠点
- #物流業界
- #物流総合効率化法
- #物流課題
- #特殊倉庫
- #用途地域
- #異物混入
- #着工床面積
- #空調
- #結露
- #耐震工事
- #職場認証制度
- #自動倉庫
- #自動化
- #自動車運送事業者
- #衛生管理
- #補助金
- #規制緩和
- #調理器具
- #貸倉庫
- #軽油
- #適正流通ガイドライン
- #関西物流展
- #防災
- #防災用品
- #防爆構造
- #集中豪雨
- #電気代
- #電気代削減方法
- #静電気
- #静電気対策
- #非危険物
- #非接触
- #食品倉庫
- #食品物流
- #食品衛生法
もっと見る▼