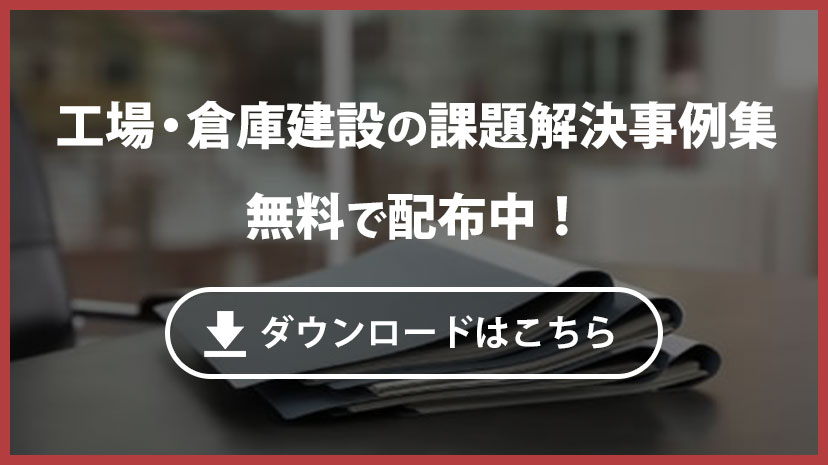物流倉庫・物流センターの新設・建設計画でおさえておきたい4つのステップと注意点!
投稿日:2019.11.09
更新日:2026.02.09
お役立ち情報

物流倉庫や物流センターを新設・建設するには、4つのステップ(基本計画・立地検討・設計・システム/施工)を漏れなく押さえることが成功のカギです。特に施工段階では、コスト・スケジュール・品質に大きく影響するため、事前の計画と管理が欠かせません。
そこで本記事では、物流センター新設における 基本の4ステップ に加え、施工フェーズの注意点 や 運営開始前後の準備・改善ポイント を、実務経験に基づく視点で具体的に整理しました。プロジェクトの全体像を把握し、効率よく進めるためのロードマップとしてご活用いただけます。
食品(医薬品)物流センターの建設で知っておくべきな情報はこちら
Contents
物流倉庫と物流センターについて
物流倉庫とは商品の保管に特化した施設のことです。従来の倉庫が主に物品の保管を目的としていましたが、物流倉庫はそれに加えて在庫管理、発送業務、商品の梱包・発送など、多岐にわたる物流機能を提供しています。
物流センターは商品の受け入れから発送までの一連の内部業務を総合的に管理する役割を持っています。製品が仕入先から到着した後は、注文が入るまで保管し、注文が確認されたらピッキング作業を行い、流通加工を施し、品質を検査した後に梱包し、出荷します。このように、始めから終わりまでのプロセスを効率的に処理できることが大きな強みです。さらに、大量の荷物を扱うため、物流センターには多数の出入り口が設けられていることが一般的です。
物流倉庫・物流センター建設・新設における4つステップと注意点
それでは、物流倉庫・物流センター建設計画が立ち上がった場合、各ステップで注意しておきたいポイントについて簡単にご紹介しておきます。ここでは、大まかにステップを分類し筆者がここはおさえておきたいと考えるポイントについてご紹介します。
ステップ1:基本計画を立てる
まずは物流倉庫を設立するためのコンセプトや基本的な設計与件を決定します。この時点でプロジェクトメンバーの選定も必要になるでしょう。
基本計画での注意点
- コンセプトと倉庫機能を明確にする
倉庫建設の目的や主機能を明確にします。これは、倉庫建設計画が立ち上がった時点で必然的に存在しているのですが、既存倉庫との相違点や新倉庫の目標値などを明確にし、それを担当者間で共通認識にしておくことが重要です。 - 必要なスペースを算出
物流倉庫・物流センター内で必要なエリアを、入荷、在庫、物流加工、仕分け、出荷待機などの大まかなカテゴリに分類します。そして、これらの分類ごとに必要なスペースを計算していきます。例えば、在庫スペースは商品のカテゴリーや梱包の形態(ケースや個別商品)、リザーブエリアとピッキングエリアなど、それぞれ毎に算出されます。 - 倉庫キャパシティの設定
新たに建設する倉庫の出荷件数や在庫物量など、倉庫キャパシティの設定が必要になります。万一、キャパシティオーバーした場合の対応策なども詰めておく必要があるでしょう。 - 目標値などの設定
顧客サービスやリードタイムなどの目標値の設定を行います。目標値に関しては、自社の都合のみで考えるのではなく、他社との競争や業界の特性を踏まえた上で設定する必要があります。
ステップ2:立地の検討
新倉庫建設にふさわしい立地を絞り込む必要があります。地域の絞り込みは以下の点に注意しましょう。
立地検討での注意点
- 交通アクセス条件
物流倉庫は交通アクセス条件が重要です。高速のIC、空港、港湾など、交通アクセス拠点との距離などをチェックする必要があります。 - 用地条件
建築基準法や消防法、用途など、物流倉庫の建設ができる用地を探す必要があります。 - 他の物流拠点との関係
自社の物流拠点が複数になる場合、各拠点の配送地域や配送先数を考慮する必要があります。 - 人員確保、作業員の通勤条件
倉庫内作業員の確保のしやすさも重要です。
ステップ3:ブロックレイアウト
新たに建設する倉庫において、商品分類や荷姿(ケース、バラ、パレット等)、カテゴリーなどの設計基礎データを確定し、倉庫の基本的な運用が決まれば、倉庫のブロックレイアウトを考えなければいけません。
ブロックレイアウトでの注意点
- 各スペースについて
物流倉庫の場合、入荷、荷捌き、在庫、仕分け、出荷待機など、各作業のためのスペースが必要になります。したがって、倉庫内で各作業ごとに必要になるスペースを算出する必要があるでしょう。既存物流倉庫が他にあるのであれば、その数値が最も参考になるでしょう。 - 入出荷バースについて
入荷バース数とトラックサイズ、出荷バース数とトラックサイズを決めなければいけません。この部分は配送スケジュールなどにも絡んでくるでしょう。 - 倉庫内で使用する大型機器について
自動倉庫システムの導入などであれば、機器そのものの設置に大きなスペースが必要になります。したがって設置スペースと作業スペースの算出は必要不可欠です。 - ブロックレイアウト図の作成
上記をもとにブロックレイアウト図を数パターン作成します。
ステップ4:導入する物流システムについて
倉庫規模や取り扱い製品によって、導入する物流システムを考えなければいけません。
物流システムの注意点
- 既存システムを活用する場合
別拠点などで、既存物流システムを利用している場合、現在の保有システムを活用できるか検討する必要があるでしょう。活用する場合、そのシステムをベースに、新たな倉庫のためのカスタマイズを考えましょう。 - 新たに物流システムを導入する場合
この場合、システムの仕様、設計、開発、導入までにそれなりの時間がかかります。倉庫建設に間に合うようにシステム開発の打ち合わせをしていきましょう。
新設物流センターの設計時に重要な業務フローとレイアウトの連動
物流センターの設計では、建物や設備の配置だけでなく、入荷から出荷までの業務フローと連動したレイアウトを考えることが重要です。動線が複雑になると作業効率が低下し、人員や時間のロスにつながります。
例えば「I字型」や「U字型」の流れを意識した配置にすることで、無駄な移動を最小化し、各工程がスムーズに連携できます。設計段階から業務プロセスを反映させることで、センター全体の生産性向上が実現できます。
ABC分析による在庫配置と動線最適化
保管効率を高めるためには、在庫を出荷頻度に応じて分類する「ABC分析」の活用が有効です。
出荷頻度の高いAランク商品は入出庫口の近くに配置することで、移動距離を短縮し、作業効率を向上できます。反対に出荷頻度が低いCランク商品は奥のスペースに配置することで、限られた面積を有効活用できます。
このように、在庫の特性に応じた配置を行うことで、動線の最適化と作業スピードの向上を同時に実現できます。
将来の変動に対応するフレキシブル設計
物流量や取扱商品の種類は、年々変化していきます。そのため、物流センターの設計段階から、将来的な拡張やレイアウト変更に対応できる柔軟性を持たせることが重要です。
例えば、スペースに余裕を残しておく、可動式ラックを導入するなどの工夫をすることで、需要の変動や新しい業務への対応がしやすくなります。将来を見据えたフレキシブルな設計が、持続的に活用できる物流センターの実現につながります。
ラック選定と通路幅の最適化
物流センターの保管能力と安全性を左右するのが、ラックの種類と通路幅の設計です。
パレットラックや高層ラックなど、取り扱う荷物の特性や搬送機器に合わせた選定を行う必要があります。さらに、通路幅はフォークリフトや台車が安全に通行できる寸法を確保しなければなりません。
効率的な保管と安全な作業環境を両立させるには、ラックと通路のバランスを考慮した設計が欠かせません。
業務フロー・要員計画・レイアウトを踏まえた設計
物流センターの設計は、単に建物の間取りを考えるだけでは不十分です。実際の業務フロー、人員配置、必要な作業工数を踏まえてレイアウトを検討することが大切です。
例えば、出荷量に応じた作業者数や、ピーク時に必要となる動線の広さを事前に試算しておくことで、無理のない運用が可能になります。業務、要員、レイアウトを一体的に検討することで、長期的に安定したセンター運営につながります。
検品精度と誤出荷防止のためのIT導入
物流センターの現場では、誤出荷防止が最も重要な課題のひとつです。そのためには、バーコードやハンディターミナルを活用したITシステムの導入が効果的です。
目視確認に頼らず、システムによるチェックを取り入れることで、検品精度を大幅に高めることができます。また、リアルタイムで在庫情報を管理することで、欠品や誤配送のリスクを減らすことも可能です。IT導入は作業効率の向上と品質確保の両立に欠かせないポイントです。
物流倉庫・物流センターの施工段階でのポイント
新設プロジェクトで特に重要となる「施工(建設)」フェーズについて、実務で押さえるべきポイントを整理します。
施工会社の選定
- 実績の確認
- 設計施工一貫の活用
- 契約条件とリスク管理
倉庫・物流センター建設実績(S造・鉄骨造・PC造)が豊富な会社を優先。マテハン導入経験も評価ポイント。
設計施工一貫方式ならコスト・工期・調整の最適化が可能。RiSOKO® のような一貫ブランドは品質管理面でも有利。
工期遅延・追加費用・仕様変更などのリスク分担を契約時に明確化しておく。
施工計画とスケジュール管理
- 主要工程の可視化
- 遅延リスクの抑制
- 品質管理体制
基礎 → 鉄骨 → 外装 → 内装・設備(マテハン、電気、空調) → 検査 → 引き渡しを詳細に計画。
季節・天候・資材の納期・職人手配など、外部要因を見込んだスケジュール調整を行う。
現場監督と外部検査の併用により、構造強度・耐荷重・安全面を確保。
安全対策と法令遵守
- 法令対応
- 構造・耐震
- 動線・作業安全
建築基準法・消防法を遵守し、商品特性(危険物・温度管理品など)に合わせた設備要件を確認。
地盤調査の実施、必要に応じた補強、耐震設計を施工会社と連携してチェック。
フォークリフト動線、高所作業の安全措置(足場・手すり)などを設計段階から確保。
設備・ラックの設置計画
- ラックと通路幅の最適化
- 耐荷重の確認
- インフラの整備
パレットラック・可動ラック・自動化対応ラックなど、設備に合わせた通路幅を確保。
重量物を扱う場合は床・ラックの強度を構造設計と連携して確認。
コンベア、AGV、ピッキング機器の電源・通信・制御システムを施工計画に反映。
物流倉庫・物流センター建設後の運営準備と改善ポイント
物流倉庫・物流センターの建設が完了しても、そのまま稼働できるわけではありません。運営開始に向けて以下の準備が必要です。
運営開始前の準備
人員の採用と教育:倉庫作業員や管理者を確保し、WMS(倉庫管理システム)の操作や安全教育を徹底します。
システム連携のテスト:WMSと基幹システム(ERPなど)のデータ連携を事前にテストし、入出荷処理の不具合を洗い出します。
試運転とシミュレーション:実際の商品を使い、入荷から出荷までの一連の流れを試運転してボトルネックを確認します。
運用開始後の改善サイクル
物流センターは稼働開始がゴールではなく、むしろスタートです。効率的な運営のためには、継続的な改善が欠かせません。
KPIの設定とモニタリング
出荷精度、リードタイム、作業生産性などを数値化し、定期的にモニタリングすることで改善点を明確化します。
現場からのフィードバック活用
作業員の意見や現場での課題を吸い上げ、改善活動に反映することが効率化に直結します。
PDCAサイクルの実践
計画(Plan)→実行(Do)→評価(Check)→改善(Action)を繰り返すことで、持続的に高いパフォーマンスを維持できます。
最新技術の導入による進化
物流業界は技術革新が早く、最新設備の導入によって競争力を高めることが可能です。
自動化技術:AGV(無人搬送車)やロボットピッキングの導入による省人化
AI活用:需要予測や在庫最適化にAIを活用
環境対応:省エネ設備や再生可能エネルギーの導入によるサステナブル経営
物流倉庫・物流センターの新設は、建設計画と同じくらい「運営準備」と「継続的改善」が重要です。事前準備を徹底し、運用開始後もKPI管理や技術導入を進めることで、効率的で持続可能な物流拠点を実現できます。
物流倉庫・物流センターの施工事例
ここでは、Risokoが設計から建設まで一貫して対応した新設物流センター・倉庫の施工事例をご紹介します。
-
冷蔵・冷凍倉庫
 株式会社萬味ホールディングス 本社施主:株式会社萬味ホールディングス株式会社萬味ホールディングス様では、物流機能の強化と業務効率向上を目的に、本社倉庫の新設を計画されました。既存倉庫では保管スペースや作業動線に課題があり、将来の物量増加にも対応できる物流拠点が求められていました。
株式会社萬味ホールディングス 本社施主:株式会社萬味ホールディングス株式会社萬味ホールディングス様では、物流機能の強化と業務効率向上を目的に、本社倉庫の新設を計画されました。既存倉庫では保管スペースや作業動線に課題があり、将来の物量増加にも対応できる物流拠点が求められていました。
RiSOKO®は設計から建設までを一貫して担当し、業務フローを踏まえた倉庫計画を提案しました。入庫から出荷までの動線を最適化し、限られた敷地を有効活用するため鉄骨造2階建としました。保管・作業エリアを明確に分け、安全性と作業効率の両立を実現しています。
設計・施工一貫体制により品質と工期を確保し、竣工後は作業効率向上と安定した物流運営に貢献するとともに、将来の運用変化にも柔軟に対応できる物流倉庫が完成しました。 -
その他倉庫
 有限会社山城陸運 久喜物流センター施主:有限会社山城陸運有限会社山城陸運 久喜物流センターは、埼玉県久喜市に新設された物流倉庫で、RiSOKO®が設計から建設まで一貫対応したプロジェクトです。RiSOKO®は物流現場の業務フローを理解した上で、現場作業の効率化と安全性を両立する設計提案を行い、計画段階からクライアントと詳細なヒアリングを重ね、最適なレイアウトと動線計画を策定しました。
有限会社山城陸運 久喜物流センター施主:有限会社山城陸運有限会社山城陸運 久喜物流センターは、埼玉県久喜市に新設された物流倉庫で、RiSOKO®が設計から建設まで一貫対応したプロジェクトです。RiSOKO®は物流現場の業務フローを理解した上で、現場作業の効率化と安全性を両立する設計提案を行い、計画段階からクライアントと詳細なヒアリングを重ね、最適なレイアウトと動線計画を策定しました。
倉庫は鉄骨造の平屋建てとして構築され、入庫・保管・出荷の各ゾーンが明確に分けられています。これにより作業負荷の軽減と業務のスムーズな進行を実現しています。設計・施工一貫体制により、設計意図を忠実に反映した施工が進められ、品質・安全基準を満たす物流施設が完成しました。 -
その他倉庫
 親和パッケージ株式会社 藤沢ロジスティクスセンター(藤沢市)施主:親和パッケージ株式会社親和パッケージ株式会社 藤沢ロジスティクスセンターは、神奈川県藤沢市に新設された物流倉庫で、RiSOKO®が設計から施工まで一貫して対応した事例です。
親和パッケージ株式会社 藤沢ロジスティクスセンター(藤沢市)施主:親和パッケージ株式会社親和パッケージ株式会社 藤沢ロジスティクスセンターは、神奈川県藤沢市に新設された物流倉庫で、RiSOKO®が設計から施工まで一貫して対応した事例です。
RiSOKO®は、倉庫運用の現場ニーズを踏まえたオーダーメイドの設計提案を行い、現場作業の効率性や安全性を高めるレイアウト計画を実施しました。本施設はS造の平屋建て(一部2階建)で、入庫・保管・出荷それぞれのエリアを明確にゾーニングし、物流動線を最適化しています。
設計段階から現場業務を理解した上で施工され、仕様・法令対応まで一貫した体制で進められたことで、高品質な物流機能を備えた倉庫が完成しました。 -
危険物倉庫
 山九株式会社 北勢第3物流センター山九株式会社三重県菰野町に建設された「山九株式会社 北勢第3物流センター」は、危険物の安全管理と効率的な物流運用を両立するために新設された危険物倉庫です。本施設は、RiSOKO®が設計から建設まで一貫して対応し、危険物倉庫に求められる法令遵守と実運用を見据えた空間設計を実現しました。
山九株式会社 北勢第3物流センター山九株式会社三重県菰野町に建設された「山九株式会社 北勢第3物流センター」は、危険物の安全管理と効率的な物流運用を両立するために新設された危険物倉庫です。本施設は、RiSOKO®が設計から建設まで一貫して対応し、危険物倉庫に求められる法令遵守と実運用を見据えた空間設計を実現しました。
建物は鉄骨造平屋建て4棟で構成され、総延床面積は約3,879㎡。危険物第4類を対象とし、各棟で指定数量の200倍超に対応する保管能力を確保しています。設計段階から消防法をはじめとする関連法規への対応を徹底し、安全性と将来の運用効率を考慮した計画としました。さらに、木造の事務所棟を併設することで、管理業務と現場運用を円滑に行える体制を構築しています。 -
冷蔵・冷凍倉庫
 株式会社手原産業倉庫 栗東チルドセンター株式会社手原産業倉庫株式会社手原産業倉庫 栗東チルドセンターは、滋賀県栗東市に新設された冷蔵倉庫であり、RiSOKO®が設計から建設まで一貫対応した物流施設です。施主である株式会社手原産業倉庫のニーズに応え、定温管理が必要な物流機能を備えるため、倉庫全体を冷蔵倉庫として設計・施工しました。建物は鉄骨造の平屋建てで、延床面積は1,806.44㎡。
株式会社手原産業倉庫 栗東チルドセンター株式会社手原産業倉庫株式会社手原産業倉庫 栗東チルドセンターは、滋賀県栗東市に新設された冷蔵倉庫であり、RiSOKO®が設計から建設まで一貫対応した物流施設です。施主である株式会社手原産業倉庫のニーズに応え、定温管理が必要な物流機能を備えるため、倉庫全体を冷蔵倉庫として設計・施工しました。建物は鉄骨造の平屋建てで、延床面積は1,806.44㎡。
RiSOKO®は、物流業務の特性を踏まえたレイアウト設計や温度管理機能の最適化、施工品質の確保までを一貫してサポートすることで、食品や温度管理が必要な商品の安全で効率的な保管・出荷を実現しました。
物流倉庫・物流センターの設計に関するよくある質問
ここでは物流倉庫と物流センターの設計に関するよくある質問をご紹介します。
物流倉庫と物流センターの設計は何が違いますか?
物流倉庫は「保管」が主目的であるのに対し、物流センターは入庫・保管・ピッキング・出荷までの業務フロー全体を最適化する設計が求められます。そのため物流センター設計では、動線計画や作業効率、ITシステム連携まで含めた設計が重要になります。
将来の物量増加を見据えた設計は可能ですか?
可能です。物流センター設計では、将来の拡張や業務変更を前提とした柔軟性を持たせることが重要です。
可動式ラックの採用や、増設可能なスペースを確保することで、物量変動にも対応しやすくなります。
物流センターの建設計画にはどのくらいの期間が必要ですか?
規模や内容によりますが、基本計画から稼働開始まで1~2年程度かかるケースが一般的です。
初期検討、設計、各種申請、建設工事、運営準備までを含め、余裕を持ったスケジュール策定が必要です。
建設計画の段階で設計はどこまで詰める必要がありますか?
建設計画段階では、業務フローを前提とした基本設計レベルまで検討しておくことが理想です。
レイアウトや動線を考慮せずに建設を進めると、稼働後に大きな手戻りが発生する可能性があります。
まとめ
今回は、新たに物流倉庫建設プロジェクトが立ち上がった場合に注意しておきたいポイントについてご紹介しました。本稿では、建設会社など、専門業者に依頼する以前に、自社のプロジェクトメンバーで最低限おさえておかなければいけないポイントを中心にご紹介しました。もちろん、上記でご紹介した内容以外にも多くの注意ポイントが存在していると考えておかなければいけません。
関連記事:倉庫建設を検討中なら、システム建築のメリットと制約をおさえておきましょう
実際に建設計画を進めていく場合には、専門業者のアドバイスも受けることになりますが、上述したような自社内でのコンセプトや最低限の基本計画が無ければ、打ち合わせに時間ばかりを取られて、スムーズにプロジェクトが進まなくなってしまう恐れもあるでしょう。「専門業者が何もかも導けば良いのでは?」と思うかもしれませんが、自社に最適な施設を建設しようと思う場合には、「なぜそれが必要なのか?」をきちんと明確にしておかなければ、アドバイスのしようがない場合もあるのです。
何から考えていけばいいかわからず、ご不安な方は三和建設へご相談ください。倉庫建設をプロデュースいたします。
定温倉庫をはじめ倉庫の種類や機能別倉庫の設計・建築方法についてはこちら
関連記事
ARCHIVE
TAG
- #バーコードリーダー
- #IoT機器
- #冷凍
- #冷蔵
- #リノベーション
- #法改正
- #冷蔵冷凍倉庫
- #発注
- #断熱
- #冷却
- #改正物流効率化法
- #物流統括監理者
- #倉庫業法施行規則
- #温度区分
- #太陽光パネル
- #食品物流センター
- #動画開設
- #配棟計画
- #パレット共通化
- #レンタルパレット
- #大阪万博
- #建築費動向
- #トラックGメン
- #ブラック荷主
- #物流クライシス
- #建設準備
- #グラフ
- #建築費
- #ドライバー不足
- #立地
- #2024年問題
- #3PL
- #3温度帯
- #4温度帯
- #AGV
- #AI
- #AVG
- #CAS冷凍
- #EC
- #FSSC22000
- #GDPガイドライン
- #IoT
- #IT
- #LED
- #RiSOKOセミナー
- #Society 5.0
- #Third Party Logistics
- #エアコン
- #カーボンニュートラル
- #ガソリン
- #グッズ
- #コールドチェーン
- #コロナ
- #コロナ禍
- #システム建築
- #タグを削除: RiSOKOセミナー RiSOKOセミナー
- #デバンニング
- #トラック待機時間
- #バンニング
- #ひさし
- #ピッキング
- #フォークリフト
- #プラスチック削減
- #フルフィルメント
- #プロトン凍結
- #フロン排出抑制法
- #フロン管理義務
- #マテハン
- #マテハン機器
- #メディカル物流
- #ラック
- #リチウムイオン蓄電池
- #ロボット
- #ロボット化
- #中小企業支援策
- #事故事例
- #人手不足
- #人材不足
- #低温倉庫
- #低温物流
- #保安距離
- #保有空地
- #保管効率
- #保管場所
- #保管温度帯
- #倉庫
- #倉庫の強度
- #倉庫の種類
- #倉庫建設
- #倉庫建設コンサルタント
- #倉庫新築
- #倉庫業法
- #倉庫火災
- #免震
- #共同物流
- #冷凍倉庫
- #冷凍自動倉庫
- #冷凍食品
- #冷蔵倉庫
- #冷蔵庫
- #削減
- #労働時間
- #労働災害
- #医療機器
- #医療物流
- #医薬品
- #医薬品の物流業務
- #医薬品保管
- #医薬品倉庫
- #危険物
- #危険物倉庫
- #危険物施設
- #営業倉庫
- #国際規格
- #土地
- #地震
- #地震対策
- #基礎知識
- #安全
- #安全対策
- #定期点検
- #定義
- #対策
- #屋内タンク貯蔵所
- #屋内貯蔵所
- #工場
- #工場の衛生管理
- #建築基準法施行令
- #建設計画
- #従業員
- #感染予防
- #技術
- #換気設備
- #改修工事
- #政令
- #新型コロナウイルス
- #新築
- #施設設備基準
- #機能倉庫建設
- #水害
- #水害対策
- #治験薬
- #法律
- #消防法
- #消防設備
- #温度管理
- #火災
- #火災対策
- #災害
- #無人搬送ロボット
- #無人搬送車
- #無人配送車
- #燃料費
- #物流
- #物流DX
- #物流センター
- #物流倉庫
- #物流倉庫新設
- #物流倉庫自動化
- #物流拠点
- #物流業界
- #物流総合効率化法
- #物流課題
- #特殊倉庫
- #用途地域
- #異物混入
- #着工床面積
- #空調
- #結露
- #耐震工事
- #職場認証制度
- #自動倉庫
- #自動化
- #自動車運送事業者
- #衛生管理
- #補助金
- #規制緩和
- #調理器具
- #貸倉庫
- #軽油
- #適正流通ガイドライン
- #関西物流展
- #防災
- #防災用品
- #防爆構造
- #集中豪雨
- #電気代
- #電気代削減方法
- #静電気
- #静電気対策
- #非危険物
- #非接触
- #食品倉庫
- #食品物流
- #食品衛生法
もっと見る▼