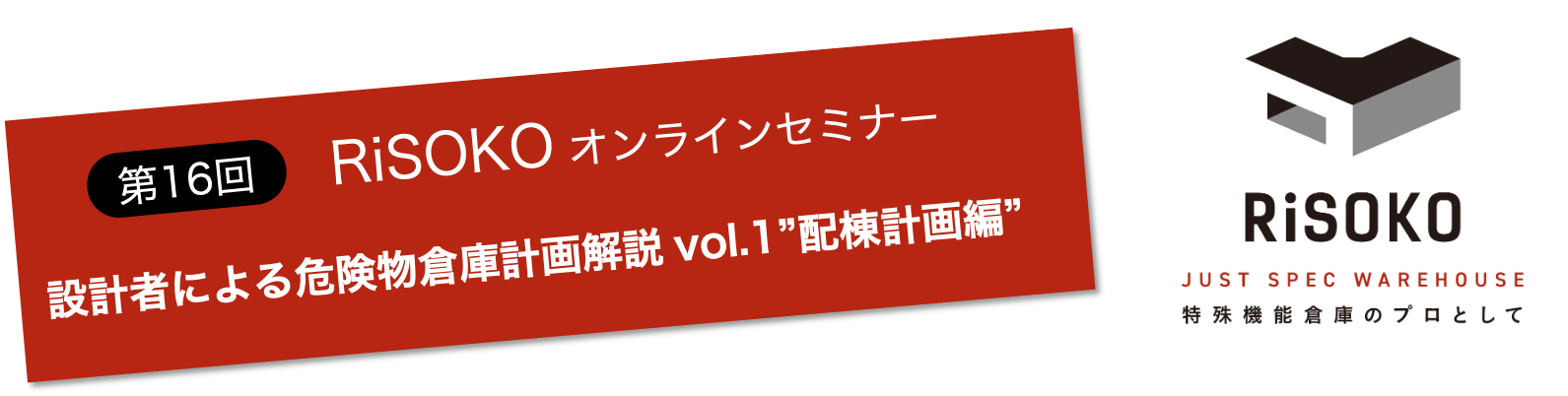消防法で定める危険物の種類・等級・総量・表示規制を解説
投稿日:2019.08.08
更新日:2024.03.21
お役立ち情報

今回は、法律で定義されている『危険物』とはどのような物なのかについてご紹介します。『危険物』という言葉は、普段何気なく使っていたり、耳にしたりするものですが、その危険物がどのような物質なのか?や、どのような分類があるのか?ということはご存知でしょうか?言葉の意味をそのまま取ると「何らかの危険があるもの」となりますので、一般生活の中で考えるとかなり多くのものが『危険物』に分類されそうなものです。
一般的にですが、危険物と聞けば毒物や劇物をイメージする人が多いと思います。しかし、倉庫や工場の運営において『危険物』と表現する場合には、消防法に定められているものを指しており、消防法では引火・発火性がある、燃焼を促進させる、中毒を引き起こすなど、大きな災害の原因となりうる物質を危険物と指定しています。もちろん、こういった危険物を大量に取り扱う場合には、法律や条例などが定めている危険物の分類による表示・総量・表示などの厳しい基準を満たし、特別に許可を得る必要があるのです。
そこで本稿では、危険物の基礎知識として「消防法に定められている危険物の種類は何か?」についてご紹介します。危険物を正しく安全に取り扱うためには、必ずおさえておかなければならない情報ですので、ぜひ参考にしてください。
Contents
危険物の定義とは?

それではまず、危険物の定義を簡単にご紹介しておきましょう。冒頭でご紹介したように、危険物は、火災・爆発・中毒を引き起こす危険性がある物質の総称です。法律の面からみると、消防法上の『危険物』と毒物及び劇物取締法上の『危険物』があるのですが、倉庫や工場の運営に大きくかかわるのは「消防法上の危険物」となります。
消防法というは、言葉は誰もが聞いたことがあると思いますが、これは以下の目的のために作られた法律です。
火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もって安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを目的とする。
消防法は、上記のように「火災の予防・警戒・鎮圧による国民の生命・身体・財産の保護・被害軽減」が目的として定められており、この中で以下のものを危険物として定義し、その保管方法や運送方法を厳密に定めているのです。
- 火災発生の危険性が大きい物品
- 火災が発生した場合に火災を拡大する危険性が大きい物品
- 火災の際の消火の困難性が高いなどの性状を有する物品
消防法に定められている危険物は、第 1 類 ~第 6 類までの6種類に分類されていますので、それぞれの特徴を以下でご紹介します。
消防法に定められている危険物の分類について
それでは、消防法で定められている危険物について、その分類とそれぞれの特徴をまとめてご紹介します。
第1類…酸化性固体
第1類の『酸化性固体』は、そのもの自体は燃焼しませんが、反応する相手を酸化させる性質を持った固体の総称となります。
酸化性固体は、他の物質を強く酸化させる力を持っており、可燃物と混合した場合、『熱、衝撃、摩擦』によって分解し、極めて激しい燃焼を起こさせる危険性があります。
塩素酸ナトリウム、硝酸カリウム、硝酸アンモニウムなど
第2類…可燃性固体
『可燃性固体』は、火炎によって着火しやすいまたは、40℃未満の比較的低温で引火しやすい固体のことです。この物質は、出火しやすいうえに、燃焼も速いことから、いったん燃えてしまうと消火するのが非常に困難という特徴があります。また、酸化されやすい物質ですので、酸化性物質と混合・接触されると、発火、爆発の危険性があります。
赤リン、硫黄、鉄粉、固形アルコール、ラッカーパテなど
第3類…自然発火性物質及び禁水性物質
『自然発火性物質』は、空気にさらされることで自然発火しやすい固体や液体のことです。『禁水性物質』は、水と接触することで発火もしくは可燃性ガスを発生させる固体や液体です。『禁水性物質』は、火災が起きた時に水をかけて消火しようとすると、余計に悪化する恐れがあるため、粉末消火剤による窒息消火が必要です。
ナトリウム、アルキルアルミニウム、黄リンなど
第4類…引火性液体
『引火性液体』は、その言葉通り引火性を有する液体のことです。この中には、可燃性の蒸気を発するものもあり、点火源(火気、火花、静電気、摩擦熱)が近くにあるだけで、引火・爆発を起こす危険性があります。
ちなみに、第4類の危険物については、消防法別表で以下のように規定されています。
| 種目 | 性状指定 |
|---|---|
| 特殊引火物 | ・1気圧において、発火点が100℃以下のもの ・1気圧において、引火点が-20℃以下で、かつ沸点が40℃以下のもの |
| 第1石油類 | 1気圧において、引火点21℃未満のもの |
| アルコール類 | 炭素数1~3までの飽和1価アルコールで、変性アルコールを含む |
| 第2石油類 | 1気圧において、引火点が21℃以上、70℃未満のもの |
| 第3石油類 | 1気圧において、引火点が70℃以上、200℃未満のもの |
| 第4石油類 | 1気圧において、引火点が200℃以上、250℃未満のもの |
| 動植物油類 | 引火点250℃未満の動物の脂肉等又は植物の種子、果肉から抽出した液体 |
ガソリン、灯油、軽油、重油、アセトン、メタノールなど
第5類…自己反応性物質
『自己反応性物質』は、自己燃焼しやすい固体や液体のことです。この物質は、燃焼に必要な3つの要素とされる「可燃物」「酸素供給体」「点火」のうち、可燃性と酸素供給体の2つを含んでいます。そのため、空気に触れていなくても燃焼が進み、比較的低い温度で多量の熱を発生する、また爆発的に反応が進むという特徴を持っています。摩擦や衝撃、直射日光などでも発火する等、非常にデリケートな物質です。
ニトログリセリン、トリニトロトルエン、ヒドロキシルアミンなど
第6類…酸化性液体
そのもの自体が単独で燃焼することはない液体ですが、混在する他の可燃物の燃焼を促進させる性質を持っています。反応する相手を酸化させる性質を持っているため、保管の際は、耐酸性の容器を使用、取扱の際は保護具をつける必要があります。
過塩素酸、過酸化水素、硝酸など
消防法上の危険物施設について
厚生労働省の【消防法における危険物の取扱いについて】において、「消防法上の危険物施設」の定義について以下の様に書いていおります。
“消防法で指定された数量(以下「指定数量」という。)以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う施 設は、以下のとおり、製造所、貯蔵所及び取扱所の3つに区分されています。 【製造所】 危険物を製造する目的で指定数量以上の危険物を取り扱うため市町村長等の許可を受けた場所 をいいます。 【貯蔵所】 指定数量以上の危険物を貯蔵する目的で市町村長等の許可を受けた場をいいます。 【取扱所】 危険物の製造以外の目的で、危険物を取り扱う場所をいいます。 ・給油取扱所(ガソリンスタンド) ・販売取扱所(店舗において容器入りのままで販売するため危険物を取り扱います。) ・移送取扱所(危険物を送るパイプライン) ・一般取扱所(上記以外の施設)”
危険物の保管方法について
消防法で規定された指定数量以上の危険物は、危険物貯蔵所として認可された施設において保管しなくてはなりません。消防法第10条第1項では、指定数量以上の危険物の貯蔵、取扱いについて、基準を満たした貯蔵所以外の場所での貯蔵、製造所、貯蔵所、取扱所以外の場所での取扱いは禁止されています。
6分類の危険物の取扱いや保管に関してご紹介しましたが、こういった危険物を保管する際は是非危険物倉庫建設のRiSOKOにお問い合わせください。正しく保管し、安全かつ長持ちする保管方法もご提案致します。
参考資料:厚生労働省「消防法における危険物の取扱いについて」より
危険物の指定数量
危険物の保管を行う上では指定数量についても知っておく日調があります。
ここでは危険物の指定数量についてご説明していきます。
指定数量とは?
指定数量は、「危険物についてその危険性を勘案して政令で定める数量」(消防法第9条の3)と定義されています。
この指定数量は、物質の種類や取り扱い方法によって異なります。例えば、引火性のある液体や気体、爆発性のある物質、毒性のある物質など、危険性の度合いによって指定数量が設定されています。
定められた指定数量を超える危険物の貯蔵や取り扱いは、危険物取扱者の資格を持つ者を配置する必要があるほか、防火や爆発、中毒などの危険を防止するための措置を講じることが求められます。また、指定数量に応じて、危険物の取り扱いに関する届出や許可などの手続きが必要となる場合があります。
指定数量の倍数
保管や取り扱いを行う危険物の量が指定数量の何倍であるかを計算したものが「指定数量の倍数」です。
指定数量の倍数は以下の式で求められます。
危険物の量/指定数量=指定数量の倍数
この倍数が1以上になる場合、「指定数量以上の危険物がある」ことになり、消防法の適用(消火設備の設置 、種類・数量の届け出、管理者の選任、定期点検の実施など)を受ける必要があります。
例えば、ガソリン100L、軽油500L、重油500Lを同一倉庫で保管する場合の指定数量の倍数は
となり指定数量の倍数は1以上となるため消防法の規制が必要であると判断されます。
消防法で定められる危険物の指定数量
消防法では以下のように指定数量を定めています。
| 類別 | 品名 | 性質 | 指定数量 |
|---|---|---|---|
| 第1類 | 第1類酸化性固体 | 50キログラム | |
| 第2類酸化性固体 | 300キログラム | ||
| 第3類酸化性固体 | 1,000キログラム | ||
| 第2類 | 硫化りん | 100キログラム | |
| 赤りん | 100キログラム | ||
| 硫黄 | 100キログラム | ||
| 第1類可燃性固体 | 100キログラム | ||
| 鉄粉 | 500キログラム | ||
| 第2類可燃性固体 | 500キログラム | ||
| 引火性固体 | 1,000キログラム | ||
| 第3類 | カリウム | 10キログラム | |
| ナトリウム | 10キログラム | ||
| アルキルアルミニウム | 10キログラム | ||
| アルキルリチウム | 10キログラム | ||
| 第1類自然発火性物質及び禁水性物質 | 10キログラム | ||
| 黄りん | 20キログラム | ||
| 第2類自然発火性物質及び禁水性物質 | 50キログラム | ||
| 第3類自然発火性物質及び禁水性物質 | 300キログラム | ||
| 第4類 | 特殊引火物 | 50リットル | |
| 第1石油類 | 非水溶性液体 | 200リットル | |
| 水溶性液体 | 400リットル | ||
| アルコール類 | 400リットル | ||
| 第2石油類 | 非水溶性液体 | 1,000リットル | |
| 非水溶性液体 | 2,000リットル | ||
| 第3石油類 | 非水溶性液体 | 2,000リットル | |
| 非水溶性液体 | 4,000リットル | ||
| 第4石油類 | 6,000リットル | ||
| 動植物油類 | 10,000リットル | ||
| 第5類 | 第1類自己反応性物質 | 10キログラム | |
| 第2類自己反応性物質 | 100キログラム | ||
| 第6類 | 300キログラム |
危険物の表示・ラベル
危険物を取り扱う場合には、危険物の種類や危険性を示す表示・ラベルを貼り付けることが求められます。これは、周囲の人々が危険物の種類や危険性を理解し、安全に取り扱うための措置です。以下に、危険物の表示・ラベルについて詳しく説明します。
危険物の表示
危険物の表示には、標識、旗、看板、チャートなどがあります。標識は、特定の危険物が存在することを示すために使用され、旗は、危険物が特定の場所にあることを示すために使用されます。看板は、危険物が使用されている場所に掲示され、危険物の種類や危険性、適切な取り扱い方法などを示します。チャートは、危険物の種類や危険性、取り扱い方法、緊急時の対応などをまとめたもので、施設の中心部などに掲示されることがあります。
危険物のラベル
危険物のラベルには、製品名、危険物の種類、危険性、取り扱い方法、保管方法などが表示されます。ラベルには、世界的に統一された「GHS(Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)」が採用されており、安全対策の国際的な共通化が進められています。
GHSでは、危険物の種類に応じて、特定の記号や色を使用することで、危険性を視覚的に示します。また、危険物の種類や危険性によって、ラベルに表示される情報が異なります。例えば、爆発性物質の場合には、爆発の危険性を示す記号が表示され、火気の使用や衝撃、振動などの制限が記載されます。
危険物の保管・運搬方法
危険物の保管や運搬には、適切な方法が求められます。以下に、危険物の保管・運搬方法について詳しく説明します。
危険物の保管方法
指定数量以上の危険物は、危険物貯蔵所として認可された施設での保管が求められます。
指定数量以上の危険物は、基準を満たした貯蔵所以外の場所での貯蔵、製造所、貯蔵所、取扱所以外の場所での取扱いは禁止されています。
例外として、消防本部長、消防署長の承認を受けた場合は、指定数量以上の危険物を10日以内の期間に限定して貯蔵、取扱うことが許可されます。
危険物の運搬方法
危険物の運搬や移送は指定数量未満の危険物であっても消防法の規制適用範囲となります。
危険物を移送する際には、資格を有する危険物取扱者が乗車し、免状の携帯が必要です。
また、危険物を運搬する車両には、適切な警告表示や安全装置を取り付けることや、万一の事故に備え、適切な消火器や救急箱を準備しておく必要があります。
危険物の取扱に必要な資格
一定数量以上の危険物を取扱う場合は、法律に基づき以下のような資格が必要です。
特定の危険物の取扱いに必要な免許です。
危険物の貯蔵・搬送・積込・荷役・降ろし作業などに必要な免許です。
乙種危険物取扱者免許と丙種危険物取扱者免許の両方を持つ免許です。
取扱うことができる危険物の種類や権限は甲種、乙種、丙種の3段階で違いがありますので、業務を行う中で必要な資格を取得するようにしましょう。
一般財団法人 消防試験研究センター
関連記事
危険物とは?危険物施設の種類と違いをご紹介
危険物倉庫とは?危険物保管には特別な許可を得る必要がある
まとめ
今回は、消防法に定められている危険物の種類と、それぞれの特徴についてご紹介しました。本稿でご紹介したような危険物の取り扱いは、消防法や各市町村の条例・規則によって厳しくルールが定められており、工場や倉庫において爆発や火災のリスクを低減するためには、そのルールを遵守する義務があります。とはいえ、危険物の適切な取り扱い、貯蔵、保管方法、保管総量、危険物表示、規制などに精通した人材を育成していくのは容易ではありません。したがって、こういった危険物を取り扱う場合には、危険物の保管や貯蔵のための建物や設備に精通したプロの力を活用するのが有効な手段となります。
三和建設は、危険倉庫の建設実績を多く持ち、専門的で複雑な法令を熟知したスタッフが依頼主の利便性やニーズに合わせた危険物倉庫建設の提案を行っております。
危険物倉庫の施工事例はこちら
関連記事:危険物施設の定期点検に関する基礎知識
危険物倉庫とは?建設する際の基準と押さえておくべき法令をご紹介
関連記事
ARCHIVE
TAG
- #食品物流センター
- #動画開設
- #配棟計画
- #パレット共通化
- #レンタルパレット
- #大阪万博
- #建築費動向
- #トラックGメン
- #ブラック荷主
- #物流クライシス
- #建設準備
- #グラフ
- #建築費
- #ドライバー不足
- #立地
- #2024年問題
- #3PL
- #3温度帯
- #4温度帯
- #AGV
- #AI
- #AVG
- #CAS冷凍
- #EC
- #FSSC22000
- #GDPガイドライン
- #IoT
- #IT
- #LED
- #RiSOKOセミナー
- #Society 5.0
- #Third Party Logistics
- #エアコン
- #カーボンニュートラル
- #ガソリン
- #グッズ
- #コールドチェーン
- #コロナ
- #コロナ禍
- #システム建築
- #タグを削除: RiSOKOセミナー RiSOKOセミナー
- #デバンニング
- #トラック待機時間
- #バンニング
- #ひさし
- #ピッキング
- #フォークリフト
- #プラスチック削減
- #フルフィルメント
- #プロトン凍結
- #フロン排出抑制法
- #フロン管理義務
- #マテハン
- #マテハン機器
- #メディカル物流
- #ラック
- #リチウムイオン蓄電池
- #ロボット
- #ロボット化
- #中小企業支援策
- #事故事例
- #人手不足
- #人材不足
- #低温倉庫
- #低温物流
- #保安距離
- #保有空地
- #保管効率
- #保管場所
- #保管温度帯
- #倉庫
- #倉庫の強度
- #倉庫の種類
- #倉庫建設
- #倉庫建設コンサルタント
- #倉庫新築
- #倉庫業法
- #倉庫火災
- #免震
- #共同物流
- #冷凍倉庫
- #冷凍自動倉庫
- #冷凍食品
- #冷蔵倉庫
- #冷蔵庫
- #削減
- #労働時間
- #労働災害
- #医療機器
- #医療物流
- #医薬品
- #医薬品の物流業務
- #医薬品保管
- #医薬品倉庫
- #危険物
- #危険物倉庫
- #危険物施設
- #営業倉庫
- #国際規格
- #土地
- #地震
- #地震対策
- #基礎知識
- #安全
- #安全対策
- #定期点検
- #定義
- #対策
- #屋内タンク貯蔵所
- #屋内貯蔵所
- #工場
- #工場の衛生管理
- #建築基準法施行令
- #建設計画
- #従業員
- #感染予防
- #技術
- #換気設備
- #改修工事
- #政令
- #新型コロナウイルス
- #新築
- #施設設備基準
- #機能倉庫建設
- #水害
- #水害対策
- #治験薬
- #法律
- #消防法
- #消防設備
- #温度管理
- #火災
- #火災対策
- #災害
- #無人搬送ロボット
- #無人搬送車
- #無人配送車
- #燃料費
- #物流
- #物流DX
- #物流センター
- #物流倉庫
- #物流倉庫新設
- #物流倉庫自動化
- #物流拠点
- #物流業界
- #物流総合効率化法
- #物流課題
- #特殊倉庫
- #用途地域
- #異物混入
- #着工床面積
- #空調
- #結露
- #耐震工事
- #職場認証制度
- #自動倉庫
- #自動化
- #自動車運送事業者
- #衛生管理
- #補助金
- #規制緩和
- #調理器具
- #貸倉庫
- #軽油
- #適正流通ガイドライン
- #関西物流展
- #防災
- #防災用品
- #防爆構造
- #集中豪雨
- #電気代
- #電気代削減方法
- #静電気
- #静電気対策
- #非危険物
- #非接触
- #食品倉庫
- #食品物流
- #食品衛生法
もっと見る▼