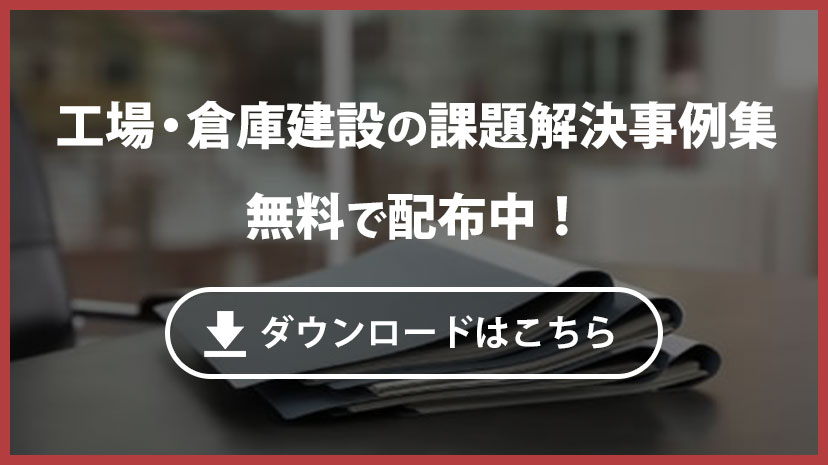危険物施設の定期点検に関する基礎知識
投稿日:2019.10.20
更新日:2024.04.26
お役立ち情報

危険物施設の異常を早期に発見するためには、日常点検はもちろん、定期点検を適正に実施することが重要です。
そこで今回は、危険物施設に必要になる定期点検の基礎知識を簡単に解説していきます。指定数量を超える危険物を製造している…取り扱っていると言うような施設の場合、定期的な点検が必要になります。そもそも危険物施設は、「通常の状態で保管・放置しておくと、引火性・発火性があり、火災や爆発、中毒などの災害につながる危険がある物質」と定義される危険物を取り扱うための施設となるため、さまざまな厳しい基準が設けられているのです。
当然、施設の老朽化に気付かず放置してしまった場合には、近隣住宅にまで被害を及ぼすような大事故に発展しかねませんし、常に万全な状態を保つためには定期的な施設の点検・メンテナンスを進めることがとても重要です。危険物倉庫で働く人の中には、「危険物の貯蔵や製造、取り扱いを行っている施設では、具体的にどのような定期点検が必要なのか知りたい」と考えている方もいると思います。
そこで今回は、危険物施設における定期点検の基礎知識を解説していきます。
Contents
定期点検の基礎知識としておさえておきたいポイント
それではまず、危険物施設における定期点検の基礎知識をご紹介します。危険物とは、冒頭でご紹介したように「通常の状態で保管・放置しておくと、引火性・発火性があり、火災や爆発、中毒などの災害につながる危険がある物質」と定義されており、一般の人でも日常的に利用するガソリンなども含まれます。通常の工場や倉庫などであっても、機械設備の燃料として一定の量は必ず保管しているという場合も多いでしょう。こう考えると、どのような施設でも定期点検が必要になりそうですが、そういう訳でもないのです。
危険物施設の定期点検のことを考える場合、以下のポイントをおさえておきましょう。
危険物施設の定義
危険物施設とは、危険物の製造を行ったり、貯蔵を行う施設の総称です。一般生活でも普通に利用する危険物もありますが、指定数量を超える危険物の『製造・貯蔵・取扱・保管』は必ず危険物施設で行わなければならないのです。自治体によっては、指定数量以下でも、自治体が定めている一定量を超える量を取り扱う場合は、危険物施設を利用するようにと定めている所もあると思います。危険物施設には以下のような種類があります。
- 製造所
- 貯蔵所・・・屋外、屋内、タンク、地下タンクなど
- 取扱所・・・給油取扱所、販売取扱所、移送取扱所、一般取扱所
危険物施設の定期点検を行う理由
言うまでもなく危険物施設の定期点検は「安全を確認するために行う」ものです。危険物施設は、消防法第10条第4項によって技術上の基準が定められているのですが、建築物は年月が経てば必ず劣化します。そのため、施設の位置や構造・設備などが消防法に定められている基準に適合しているのかを定期的に点検しなければいけないのです。もちろん補修の必要性がある部分はメンテナンスする必要が出ます。
定期点検と自主点検の違い
危険物施設であれば、日常的に何か不備がないか、自主的に点検しているという施設も多いことでしょう。こういった行為は、何らかの不具合が発生してしまった場合でも早期に発見することが出来るため、施設をより安全に運用することが可能になります。しかし、自主点検に関してはあくまで『自主的』に行っているだけのもので法律的な決まりはありません。一方、危険物施設の定期点検は、『消防法によって実施が義務づけられている』ものとなります。
定期点検が義務付けられる危険物施設は?
危険物施設の定期点検については、取り扱う危険物の量などで「定期点検が義務づけられる施設」と「定期点検を行わなくてもよい施設」に分かれます。ここでは、定期点検が必要になる危険物施設の基準についてご紹介します。
定期点検が義務づけられている危険物施設は?
それではまず、定期点検が義務づけられている危険物施設からです。消防法では、以下の項目に該当する危険物施設に定期点検を義務付けています。
| 製造所 | 指定数量の倍数が10以上及び地下タンクを有するもの |
|---|---|
| 屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が150以上 |
| 屋外タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が200以上 |
| 屋外貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以上 |
| 地下タンク貯蔵所 | すべての施設 |
| 移動タンク貯蔵所 | すべての施設 |
| 給油取扱所 | 地下タンクを有するもの |
| 移送取扱所 | すべての施設 |
| 一般取扱所 | 指定数量の倍数が 10 以上及び地下タンクを有するもの ※指定数量の倍数が 30 以下で、かつ、引火点が 40℃以上の第4類の危険物のみを容器に詰め替える一般取扱所を除く。 |
参考:消防庁資料より
関連記事:危険物倉庫とは?危険物保管には特別な許可を得る必要がある
定期点検が義務づけられていない危険物施設は?
一方で、定期点検を義務付けられていない危険物施設もあります。以下のような施設は、貯蔵できる危険物の量が限られるため、定期点検は義務ではありません。ただし、危険物を取り扱っていることには変わりありませんので、自主点検を行うことをおすすめします。
- 屋内タンク貯蔵所
- 簡易タンク貯蔵所
- 販売取扱所
指定数量以下でも自主点検は行うべき
危険物を保管している危険物施設の中でも、保管量が指定数量以下の場合は、点検頻度が定められていません。しかし、3ヵ月に1度は自主点検を行うことを推奨します。
自主点検チェックシート
危険物施設における定期点検の概要
それでは最後に、危険物施設の定期点検の概要をご紹介しておきます。危険物施設の定期点検については、消防法によって以下のように定められています。
第十二条 製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造及び設備が第10条第4項の技術上の基準に適合するよう維持しなければならない。
第十四条の三の2 政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、これらの製造所、貯蔵所又は取扱所について、総務省令で定めるところにより、定期に点検し、その点検記録を作成し、これを保存しなければならない。
引用:e-Gov『消防法』より
この危険物施設の定期点検は、原則として危険物取扱者の有資格者・危険物施設保安員が行うことになっています。ただし、危険物取扱者の立ち合いがあれば、無資格者でも行えます。定期点検の頻度などは以下の表を参考にしてください。
| 目 的 | 定期的に点検をして、製造所等の技術上の基準を維持する。 |
|---|---|
| 点検時期 | 原則、1年に1回以上 |
| 保存期間 | 原則、3年 |
| 点検事項 | 製造所等の位置、構造及び設備が技術上の基準(消防法第10条第4項)に適合しているか。 |
| 点検実施者 | 危険物取扱者又は危険物施設保安員(危険物取扱者の立会いがあれば、危険物取扱者以外の者でも点検可) |
| 記載事項 | 製造所等の名称、点検方法とその結果、点検年月日、点検者 |
なお、危険物施設の定期点検結果を記載する『定期点検記録表』については、自治体や所轄の消防署のホームページからダウンロードできる場合や、所轄の消防署に常備されていますので、そちらで入手すれば良いでしょう。
まとめ
今回は、危険物施設の定期点検についてご紹介しました。危険物施設とは、その名前の通り、火災や中毒の危険がある物質を製造・保管・取り扱いする施設となりますので、さまざまな厳しい基準が設けられています。危険物施設に何らかの不具合が出てしまった場合には、施設だけの問題ではなく周辺環境にも多大な影響を与えてしまう大事故になりかねませんので、常に安全に危険物の運用ができるよう注意しましょう。
関連記事
危険物倉庫とは?建設する際の基準と押さえておくべき法令をご紹介
消防法で定める危険物の種類・等級・総量・表示規制とは?
危険物の基礎知識。消防法における『非危険物』とはどんな物質?
関連記事
ARCHIVE
TAG
- #バーコードリーダー
- #IoT機器
- #冷凍
- #冷蔵
- #リノベーション
- #法改正
- #冷蔵冷凍倉庫
- #発注
- #断熱
- #冷却
- #改正物流効率化法
- #物流統括監理者
- #倉庫業法施行規則
- #温度区分
- #太陽光パネル
- #食品物流センター
- #動画開設
- #配棟計画
- #パレット共通化
- #レンタルパレット
- #大阪万博
- #建築費動向
- #トラックGメン
- #ブラック荷主
- #物流クライシス
- #建設準備
- #グラフ
- #建築費
- #ドライバー不足
- #立地
- #2024年問題
- #3PL
- #3温度帯
- #4温度帯
- #AGV
- #AI
- #AVG
- #CAS冷凍
- #EC
- #FSSC22000
- #GDPガイドライン
- #IoT
- #IT
- #LED
- #RiSOKOセミナー
- #Society 5.0
- #Third Party Logistics
- #エアコン
- #カーボンニュートラル
- #ガソリン
- #グッズ
- #コールドチェーン
- #コロナ
- #コロナ禍
- #システム建築
- #タグを削除: RiSOKOセミナー RiSOKOセミナー
- #デバンニング
- #トラック待機時間
- #バンニング
- #ひさし
- #ピッキング
- #フォークリフト
- #プラスチック削減
- #フルフィルメント
- #プロトン凍結
- #フロン排出抑制法
- #フロン管理義務
- #マテハン
- #マテハン機器
- #メディカル物流
- #ラック
- #リチウムイオン蓄電池
- #ロボット
- #ロボット化
- #中小企業支援策
- #事故事例
- #人手不足
- #人材不足
- #低温倉庫
- #低温物流
- #保安距離
- #保有空地
- #保管効率
- #保管場所
- #保管温度帯
- #倉庫
- #倉庫の強度
- #倉庫の種類
- #倉庫建設
- #倉庫建設コンサルタント
- #倉庫新築
- #倉庫業法
- #倉庫火災
- #免震
- #共同物流
- #冷凍倉庫
- #冷凍自動倉庫
- #冷凍食品
- #冷蔵倉庫
- #冷蔵庫
- #削減
- #労働時間
- #労働災害
- #医療機器
- #医療物流
- #医薬品
- #医薬品の物流業務
- #医薬品保管
- #医薬品倉庫
- #危険物
- #危険物倉庫
- #危険物施設
- #営業倉庫
- #国際規格
- #土地
- #地震
- #地震対策
- #基礎知識
- #安全
- #安全対策
- #定期点検
- #定義
- #対策
- #屋内タンク貯蔵所
- #屋内貯蔵所
- #工場
- #工場の衛生管理
- #建築基準法施行令
- #建設計画
- #従業員
- #感染予防
- #技術
- #換気設備
- #改修工事
- #政令
- #新型コロナウイルス
- #新築
- #施設設備基準
- #機能倉庫建設
- #水害
- #水害対策
- #治験薬
- #法律
- #消防法
- #消防設備
- #温度管理
- #火災
- #火災対策
- #災害
- #無人搬送ロボット
- #無人搬送車
- #無人配送車
- #燃料費
- #物流
- #物流DX
- #物流センター
- #物流倉庫
- #物流倉庫新設
- #物流倉庫自動化
- #物流拠点
- #物流業界
- #物流総合効率化法
- #物流課題
- #特殊倉庫
- #用途地域
- #異物混入
- #着工床面積
- #空調
- #結露
- #耐震工事
- #職場認証制度
- #自動倉庫
- #自動化
- #自動車運送事業者
- #衛生管理
- #補助金
- #規制緩和
- #調理器具
- #貸倉庫
- #軽油
- #適正流通ガイドライン
- #関西物流展
- #防災
- #防災用品
- #防爆構造
- #集中豪雨
- #電気代
- #電気代削減方法
- #静電気
- #静電気対策
- #非危険物
- #非接触
- #食品倉庫
- #食品物流
- #食品衛生法
もっと見る▼